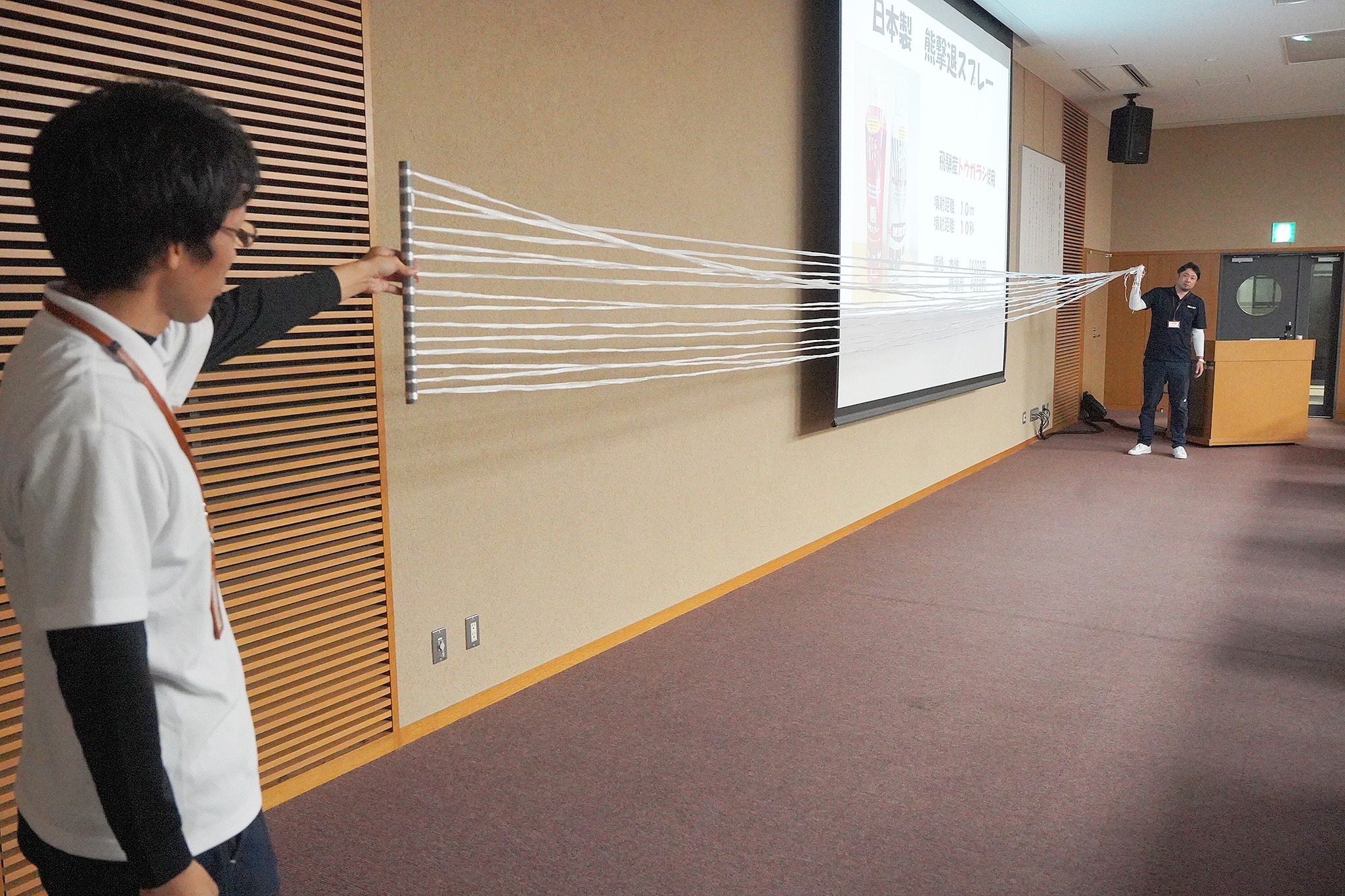クマ被害への対策を考える研修会を実施
10月8日(水曜日)、9日(木曜日) 飛騨市役所、神岡町コミュニティセンター
クマの生態について学び、人身被害や農作物への被害の防止に役立ててもらおうと、クマ対策を考える研修会が開かれました。
近年、人の生活圏へのクマの出没が多くなり、また今年は春先からクマによる人身被害や農作物被害が全国的に頻発していることを受け、クマの出没がさらに増えると考えられる晩秋を前に、クマの生態やクマの避け方などを学んでもらうもの。一般市民など約40人が参加しました。
最初に、市職員が県内での生息数が右肩あがりに増えていること、4~5年周期で大量出没が起きている状況を説明しました。神岡町内で昨年行われたクマの生息状況調査にもふれ、市街地に出没している個体は少ないと考えられる一方、市街地周辺を行動範囲にする個体が多くいる可能性を示唆。クマの出没場所が分かるアプリ「クママップ」も紹介し、「見かけたら林業振興課や警察へ情報提供を」と呼びかけました。
飛騨市鳥獣被害対策サポートセンターの原田大輔さんはクマの特性などを説明し、5~6月の繁殖期が1年でもっとも危険なこと、里に下りてくるクマは人間に会わないよう早朝や夕方、夜間に行動すること、ナトリウムが含まれるペンキの臭いを好むことなどを紹介。「里の食べ物を覚えさせないことが一番重要」と強調し、生ごみを放置しないことや収穫しない果樹を伐採することを勧めました。
また、「早朝や夕方の1人歩きは避け、川沿いや水路、やぶなどクマが隠れやすい場所は避けて」などと呼びかけました。「攻撃された時は、狙われやすい首や顔、後頭部をかばって伏せ、体をひっくり返されないよう足を広げて」などとアドバイス。クマ撃退スプレーも紹介し、届く距離などを具体的に示したりしました。
きのこ採りなどで年に3、4回は山へ入るという古川町の砂田重訓さんは「クマの好物であるドングリは、イノシシにとっても好物。イノシシが増えたことも、クマの里への出没に関係しているのでは」などと話していました。
当日の様子